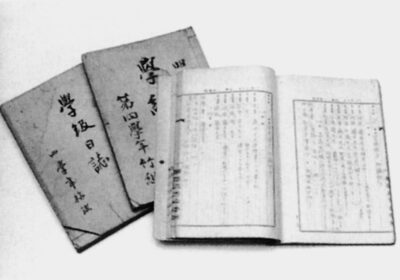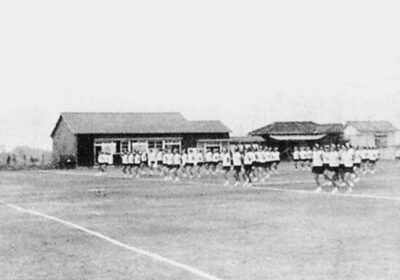100年の歩み
100年の歩み
桜蔭学園はお茶の水女子大学の前身である東京女子高等師範学校の同窓会・社団法人桜蔭会によって創立された。東京女子高等師範学校は明治8年に女子師範学校としてお茶の水に創立されて以来、女子教員養成の中枢であった。その卒業生の団体である桜蔭会は、まだ女子教育が十分とはいえない状況を憂い、理想の女子教育を実現するべく、女学校の設立を念願していた。大正12年の9月に関東大震災がおこり、東京は焦土と化したが、桜蔭会は社会報恩として女学校の設立を決め、その年の12月、桜蔭会主事会は女学校設立の議を可決した。大正13年3月には、東京府知事より桜蔭女学校設立の許可を得て、桜蔭会事務所が建っていて焼け跡になっていた本郷元町に仮校舎を建設した。平成23年3月の東日本大震災を経験し、改めて当時の桜蔭会員の熱い思いに胸を打たれる。
初代の校長には、桜蔭会の推薦により後閑キクノ先生が就任された。3月の末に入学試験を行い、第1学年100名の新入生を迎え、4月20日より授業が開始された。
桜蔭開校の様子を報道する当時の国民新聞の記事から抜粋する。
「女子高等師範の同窓会である桜蔭会が、全国2500の会員に檄を飛ばして、高等女学校の設立を企て、今年(大正13年)校舎を本郷の元町の高台に新築し、名も桜蔭女学校と、会そのままの名称で開校された。第二のお茶の水高女になる野心があるから、その意気はなかなか凄まじい。第一、後閑校長を選ぶについても、全国の会員に普選を行なって決定したくらいなのだ。先生畑の学校だけあって、優秀な先生は選り取り勝手だが、中でも山崎理学博士の夫人で、童話の作家として聞こえた光子夫人の如き、全く無報酬で習字と音楽の先生を勤めているし、体操の先生は女高師で有名な高橋きょう子女史が本校の授業の暇をみてユニホームを着たまま駆けつけて教えていると云う具合で、これも桜蔭会の勢力のお蔭と云わねばならぬ。末弘厳太郞博士の令妹杉枝さんの如く奈良女高師出で津田英学塾を出て、英語と歴史を受けもつというように、新進の女の先生ばかりで、何となく男の教師の多い女学校に比べて柔らかな感じがする。」
初代校長の後閑キクノ先生(家政学専攻)は、香淳皇后陛下が久邇宮良子女王殿下として皇太子妃に内定されたとき、選ばれてご教育主任として久邇宮家にお仕えし、大正13年1月のご成婚と共にその任務を完了された。まことに識見高邁、おのずから頭の下がるお人柄であったという。校長在任7年余、昭和6年に逝去された。
第2代校長には宮川ヒサ先生(数学専攻)が就任された。その在任17年間は、日本が戦争に突入し、敗戦を迎える厳しい時代であった。学徒動員令に基づき、桜蔭高等女学校の生徒たちも軍需工場へ出動し、学校工場も設けられた。昭和20年4月、空襲により全校舎の4分の3が消失した。
昭和23年4月、東京女子高等師範学校から第3代校長の水谷年恵先生(国文学専攻)をお迎えした。先生は4期24年を勤め上げられ、被災した校舎の復旧など戦後の学園の復興と教育の発展に尽力された。現在も活用されている浅間山荘やひばりが丘グラウンドの基礎も築かれた。
昭和47年4月には、第4代校長として木村都先生(化学専攻)をお茶の水女子大学附属高等学校からお迎えした。2期12年の在任期間中に、先生は建学の精神を確認し、生徒の人間形成に心を砕かれた。また、教育環境を充実するため、隣接する読売新聞寮跡地などを学園のものとされた。現在の講堂の敷地である。西側崖地を有効利用して旧第2体育館を建設したのも先生のお力である。
昭和59年4月から教頭の赤星秀子先生(国文学専攻)が第5代校長に就任された。在任中に念願の講堂建設が行われたが、建設にあたっては、公道に講堂と東館を連絡する上空通路を設け、生徒が安全に往来できるように多大の尽力をされた。
平成2年4月、第6代校長として教頭の青柳萬里子先生(家政学専攻)をお迎えした。先生は昭和18年に着任されて以来、半世紀以上にわたって学園のためにご尽力くださった。浅間に宿泊棟を新築し、本郷では特別教室棟が完成して学園の教育環境は一段と整った。また、在職中に東京私立中学高等学校協会の副会長をはじめ、各団体の役員を歴任された。
平成9年4月、桜蔭会会長でいらした膳惠子先生(家政学専攻)が第7代校長として着任された。先生は多年にわたる家庭裁判所調停委員のご経験をいかし、生徒の心を大切に育み教育にあたられた。浅間高原あやめが原の新井戸の分水権を得て浅間山荘の水不足を解決した。創立80周年記念として建設された西館は、機能的ななかにも木材を多用し、明るくあたたかい雰囲気の校舎となっている。
平成21年4月、第8代校長として、佐々木和枝先生(化学専攻)をお迎えした。先生は本校の卒業生であり、長くお茶の水女子大学附属中学校で教鞭を執られた後、桜蔭会会長を務めていらした。平成23年3月11日の東日本大震災は、自然の脅威と人間の未熟さを改めて私たちに教えてくれた。本校では耐震補強工事を震災の前年に完了していたが、先生は生徒の教育環境の安全性を高めるべく、施設の整備に尽力された。浅間山荘食堂棟は建替えを行い、宿泊棟と渡り廊下でつながって、安全性・利便性が向上した。また、平成26年夏には非構造部材の耐震化対策工事をおこなった。その際本館の屋根瓦を洗浄・交換し、外壁塗装もおこなったため、本館建築当初の輝きを取り戻した。
平成29年4月から教頭の齊藤由紀子先生(国文学専攻)が第9代校長に就任された。先生は本校の卒業生であり、昭和56年に専任教諭として着任されて以来長きにわたり学園で国語科の質の高い教育を支え、教務主任、教頭と歴任される間には学園の諸規程の制定や改定にも力を注がれた。平成30年、令和元年の2年間で、西館外壁修繕工事を行い、灰色だった外壁が淡い桜色になり、明るい印象となった。令和2年から5年にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大により、オンラインシステム利用による家庭学習に次いで分散登校、諸行事の中止・規模縮小と不自由な時期となった。その間に校内ネットワークシステムの整備を進めた。令和3年8月に旧東館の解体を開始し、令和5年11月には100周年記念事業となる新東館建替が竣工した。新東館は西館と渡り廊下でつながり、生徒は道路を渡ることなく西館から東館、講堂へと移動することができるようになった。
創立時より大切に育まれてきた女子教育への思いは今も脈々と受け継がれている。