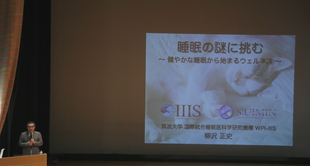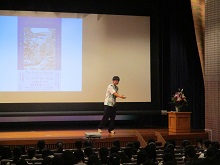中1・2対象講演会
講演会
6月10日(火)5・6時間目に、筑波大学・国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長・教授柳沢正史先生をお招きし、人生の3分の1を占める睡眠について講演をしていただきました。中1・中2対象講演会の予定でしたが、ぜひ全校生徒にと、上級生は教室中継の形で在校生全員がお話をうかがいました。IIISのコアグループ主任研究者に本校の卒業生がお二人いらっしゃるとうかがって生徒たちは一気に睡眠の謎の世界に引き込まれました。
「昼間の眠気は「異常」です」という言葉を皮切りに、睡眠不足が洞察力、学業成績、企業の業績、疾病、免疫、と様々な分野に悪影響を与えることや、眠らないと記憶を司る海馬の灰白質の容積が増えないことを教わりました。「睡眠不足は利他的行動を抑制する-つまり、寝不足だと嫌な奴になる」というデータには生徒たちからも大きな声が上がりました。
睡眠についてまだわかっていないことや、睡眠に関わる遺伝子のこと、本人は十分に寝たと思っていても実際には寝不足のケースもあるし逆に本人は不眠症だと思っていても実際には十分眠っているケースもあって、本人の感覚と客観的なデータが全く違う場合もあるということなど、「研究」という世界の面白さもたくさん教わりました。
中学生に必要な標準睡眠時間は9時間15分程度、高校生は8時間15分程度だそうです。自分にとって必要な睡眠時間を知る方法も教わりました。教室に帰る生徒たちは口々に自分の睡眠時間について話していました。ひとりひとりが自分のために今日から十分な長さの睡眠を取りましょう。